ロングエンゲージメント なぜあの人は同じ会社のものばかり買い続けるのか
ソーシャルメディアの勉強ということで読む。
ソーシャルは理論がどうのこうのより事例を示す方が具体性があってわかりやすいと思うのですが、その具体性があって読んでいてとても面白かったです。
■気になった部分
・広告コミュニケーションは共感の時代へ
・Facebookを一つの国と考えると中国、インドに次ぐ第3位の人口を持つ
・ハドソン河旅客機不時着事故×twitter
・モレスキンのブランドエピソードの表現方法
・川崎和男「橋をデザインするときに、橋をデザインしてくださいというふうな頼み方はしないでほしい」
・企業と理念と顧客のつながり
・ザッポスのコールセンターの話
・サウスウエスト航空の炎上防止事例
・ゴミをゴミ箱に捨てるようにする工夫、健康のために階段を登るようにする工夫
■感想
気になるの部分に「広告コミュニケーションは共感の時代へ」と書いたんですが、その視点を中心にどういう広告(コミュニケーション)が生まれているのか具体的な事例が掲載されています。
ソーシャルメディアが隆起してきて、企業でも「何かソーシャル対策をやらなくては・・・」というところも多いかと思います。
その際に、ただFacebookをやる、ただtwitterをやる、というのではなくこういった知識の下地と具体的にどんな事例が今までにあったのかを知っておくことが重要です。
最初にも書きましたがソーシャル関連の本は具体例がたくさん載っている方がいいと思っているので、この本はおすすめの一冊です。
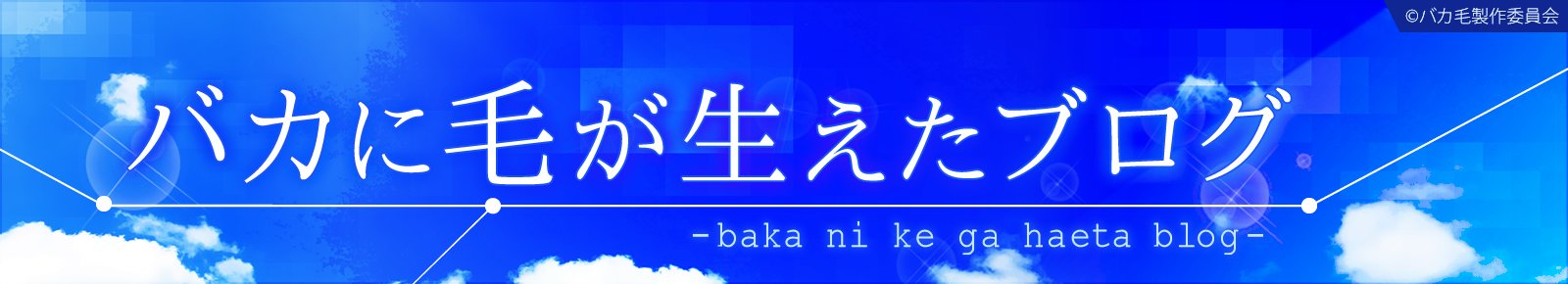
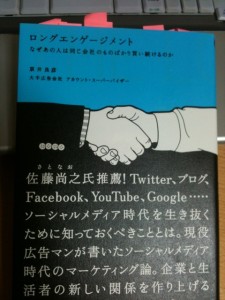

2,3回しか書き込みしてませんが、覚えていらっしゃいますか?m(__)m
「広告」や「マーケティングコミュニケーション」と「共感」というテーマは、広告論やマーケティング論でも昔から取り上げられているテーマですね。
古いのだと・・・
広告のゆくえ―共感する広告の創造
八巻 俊雄 東洋経済新報社 (1973)
・・・というのもあります。
アマゾンなどで「共感 広告」「共感 マーケティング」で検索するとけっこう出てきます。
紹介されている本を読んでないままコメントするのは大変恐縮なのですが、、、
これまで、広告やマーケティングコミュニケーションと「共感」で語られる内容というのは、企業が発するコミュニケーションメッセージ(商品や企業理念、ブランドメッセージも含め)を消費者や顧客に共感してもらう(共感させる)というのが主なものだったと思います。
でも、ソーシャルメディアが誕生した時代での「共感」の役割というのは、企業と消費者(顧客)というよりも、消費者・顧客(ユーザーと言い変えたほうが分かりやすいかも)同士の共感を高める施策のほうが向いてるような気がします。
ツイッターやFacebookだけではなく、口コミサイトなどもそうです。購入する前はもちろん、購入後も、自分が買った商品の評判や使い方などが気になることがあると思います。ユーザーの「買ってよかったよねー」というような「共感」をソーシャルメディアで具現化することで、新規顧客にも既存顧客にも影響を及ぼすメッセージを創造することができますよね。
それは、マスメディア時代に論じられた「共感」とは違うベクトルのものだと思いますし、インターネットが登場し始めた頃とも違う、ソーシャルメディアが本格的に普及してきた今だからできることかなぁと思います。
相変わらず長々とスミマセンm(__)m
こんにちは!もちろん覚えてます!
いつも素敵なコメントをありがとうございます。
企業⇔消費者
というよりも
消費者⇔消費者
と言った感じですね。
もはや企業がコントロールできる範囲もだいぶ少なくなってきていますね。
できることといえば、何かがあった際の対応、みたいな感じなんでしょうか。
というか、関連のある本をもっと読んでみます!
※
ご紹介いただいた本はもうほぼ売ってないですね。
amazonでしか見てませんが2店舗しか取り扱ってませんでした。